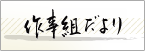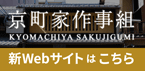上棟式で使う木槌と棟札の前で。桂離宮や青蓮院門跡など錚々たる建築物の名前が見える。後ろのヘルメットは海外のプロジェクトで現地のユニオンと記念に交換したもの。アメリカのメトロポリタン美術館日本ギャラリーなど、海外で日本の伝統建築物を手がけることもある。 ――現場監督の仕事 京都出身の大八木さんは、伏見工業高校の建築科を卒業後、設計事務所に就職。9年間勤めた後、当時おもに注文住宅を手がけていた安井杢工務店の子会社へ転職。その会社が本体と合併した時にそのまま安井杢工務店へ入社した。現場監督としてお施主さんや設計事務所と打合せをし、工程・予算管理をし、現場で施工内容をチェックする。自ら設計・施工図を書くこともある。高校に入った時は特にこの道と決めていたわけではなかったが、現在63歳、建築に携わって40年以上になる。 社内では木造、文化財、RC造、等に担当が分かれている。大八木さんは主に木造建築の現場を担当。図面を引いているより現場に出るほうが性に合っているとか。机に向かって本を開くより現場に出たほうが物を覚えるのが早いし、なにより、書いた図面が実際に出来上がっていくのを見るのが面白い。いろんな職種の職方さん達の話を聞くことができるのも勉強になって楽しい、という。 「お施主さんも、自分の家をどんな職人さんが作っているのか気になると思います。古い町家を残そうという思いのある、こだわりのある方ばかりですしね。だから直接話しかけてもらっても構いません。ただ、職人さんは口下手な人が多いですが(笑)」。 今ちょうど携わっているのはお寺の山門と鐘楼の改修工事。最近はこういった社寺の本堂以外の付属物の修復依頼が多い。大きなお寺の大改修が終わった後は、末寺からの仕事が増えるのだとか。 安井杢工務店というと数奇屋建築がよく取り上げられるが、時代の流れによって手がける建築物も変遷しているという。元々は堂宮の大工として始まった集団であるが、意外にも、高層ビル以外はなんでも造ってきた。1970年代、乙訓地域で公共施設が次々と建てられた頃には、学校や庁舎などの鉄骨やRC造も数多く施工した。 ――日本の伝統をつなぐ 安井杢工務店では、京町家を手がける場合も、重文指定になるような大店の改修が多い。文化財の場合は古いものを出来るかぎり残すというのが原則なので、古い木材でも簡単に捨てるわけにはいかない。取り替えるにしても、役所の担当課と打合せを重ねる。文化財でなくとも古いものを使うということは、それだけ手間も時間もかかる。責任が重い仕事だが、時には300年前にもなる大工の仕事を見ることができるのはとても勉強になるという。 文化財でも町家の改修でも、「直したところがわかるようではダメ」。なんとなくキレイになったな、というのがいちばん良いのだとか。お施主さんから「いったいどこを直したの?」という言葉が出たら、しめたもの。 町家の場合、最初に調査をしても解体するにつれて、腐っていたり傷みが激しかったりと、思っていたより時間も費用も余分にかかることが往々にしてある。床をはずすと囲炉裏の跡があったり、防空壕が出てくることも。「どちらかいうと改修よりも新築のほうが簡単ですよ。ある程度予測できますから」。 ――町家の住まい方 改修すればそのまま何十年ももつと考えている人が多いが、やはりメンテナンスは必要。それによって家は長持ちする。建具にしても木材は湿気で動くので、1年位はそこの気候に馴染ませながら、少々固くても辛抱して使ってもらい、1年経ったら訪問して手直しする。 気をつけないといけないのが雨漏り。漏ってすぐなら直すのも容易なので、気がついたら早めに呼んでほしい。屋根瓦は葺き替えれば50〜60年はもつ。家は閉め切るのが最も良くないので、風を通してもらうことも大切だ。冷暖房をつけ過ぎると、柱と壁の間に隙間が開いたり割れてくることもある。また、掃除をしないと家は確実に傷むという。「掃き掃除でほこりを取るぐらいで充分なんですよ」。 休みの日はたまに海釣りへ。先々代の社長が釣り好きで、昔は社内に“金太郎会”というヘラブナ釣りの同好会があったのだとか。「釣りをしていると無になれるかって?いえいえ、いろんなこと考えてますよ。釣れないのは餌が悪いのか?それとも魚がいないのか?なんて(笑)。仕事のことは完全に忘れてますけどね。」 *** メディアに度々取り上げられることもあり、自分たちの仕事が特殊なものと考えられがちで、周囲との温度差がどんどん開いてくる感じ…なんだとか。今の時代ではおそらく普通でないことを、当たり前のこととして淡々とこなされている。そんな(やっぱり)すごい職人さんが、ここにもおられました。 聞き手:常吉裕子(作事組事務局) 会社メモ 株式会社 安井杢工務店 向日市上植野町馬立2番地4 (2013.9.1) |