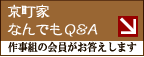チョコレート商戦が終わったデパートの食料品売り場には、雛の節句に因んだ品物が出揃う。ひちぎり・ひし餅・さくら餅・三色のお団子のほかに、練りもん屋さんにも桃や菜の花をあしらった手のひらにのるほど小さくて、可愛らしいかまぼこが彩りよく並んでいる。これらの品々も旬を過ぎれば消えてしまうのはしょうがない話なのだけれど、旧暦にお祝いをするわが家では、この時期に日持ちのするひし餅だけを買っておかなければならない。「あんたが小さいころは、四月のお節句にあわせて置いてくれはるお店があったのに。」と、母も言う。たしかに、ここは京都。ちょっと寂しい気もする。  わたしが親しんだおひなさんは四月三日。ちょうど、さくらのつぼみがほころびはじめるころに訪れた。ピンと締めていた縁のガラス戸を開けて、奥(座敷)の障子も開けると、沈丁の香りが緩んだ風といっしょに部屋のなかに運ばれてきた。さすがに、もう寒さはない。お飾りをしてもらえる嬉しさでうきうきしながら、庭先の北側にある蔵までの長い廊下を大小の木箱を抱えて行ったり来たりしたものだ。 わたしが親しんだおひなさんは四月三日。ちょうど、さくらのつぼみがほころびはじめるころに訪れた。ピンと締めていた縁のガラス戸を開けて、奥(座敷)の障子も開けると、沈丁の香りが緩んだ風といっしょに部屋のなかに運ばれてきた。さすがに、もう寒さはない。お飾りをしてもらえる嬉しさでうきうきしながら、庭先の北側にある蔵までの長い廊下を大小の木箱を抱えて行ったり来たりしたものだ。 以来、あのころの印象が体内時計にインプットされていて、三月三日のお節句がわたしにはどうもしっくりとこない。家の中にはまだ冬将軍がどっしり居座っていて、毎日は冷たい寒さの中である。庭先の藪椿も、やっとうっすらと花の色を差しはじめるものの、季節のつぼみはこっちりと固い。「奈良のお水取りが終わらんと温とうならへん。もっかい(もう一度)寒の戻りが来て、それからや。」いつも口癖みたいにして祖母がつぶやいていたけれど、それを耳にタコができるほど聞かされていたわたしは「そうかまだか。まだ春は来いひんのんか。」と、お腹の底で思って待った。さくらの便りが届くまで、おひなさんはもうちょっとの辛抱と。 以来、あのころの印象が体内時計にインプットされていて、三月三日のお節句がわたしにはどうもしっくりとこない。家の中にはまだ冬将軍がどっしり居座っていて、毎日は冷たい寒さの中である。庭先の藪椿も、やっとうっすらと花の色を差しはじめるものの、季節のつぼみはこっちりと固い。「奈良のお水取りが終わらんと温とうならへん。もっかい(もう一度)寒の戻りが来て、それからや。」いつも口癖みたいにして祖母がつぶやいていたけれど、それを耳にタコができるほど聞かされていたわたしは「そうかまだか。まだ春は来いひんのんか。」と、お腹の底で思って待った。さくらの便りが届くまで、おひなさんはもうちょっとの辛抱と。毎日のだんだん(普段)のおかずで、立春を過ぎるあたりからたびたび食卓にあがる献立に、からし和えがある。朝霜をうけて育ったお野菜は、ほんとにやわらかで初々しい春が匂ってくるようである。例えば、湯がいた畑菜をきざんでいると、菜っ葉のなかから花が出てきて「あれ!もう、薹がたってるわ!」まな板の上の菜をながめて、包丁の先でチョンチョンいじくりながら思わず声を出してしまうのもこのころだ。香ばしい胡麻と、鼻を突き抜けるからしの風味、花芽の混ざったこのおしたしを口にすると、まるで大地から芽吹きのちからをおすそ分けしてもらったような気さえしてくる。子どものころ一番苦手だったこのおかずを、今ではいそいそとこしらえたくなるのだから不思議なものだ。そういえば昔、うんと小さかった頃、菜っ葉のことを「菜々さん」と呼んでいたけれど、この時期のお野菜にはぴったりの呼び名のように思う。三寒四温、季節は行きつ戻りつを繰り返しながらヨチヨチ歩きですすんでいく。じらされながらも、その成長の過程をじっくりと楽しめる三月。この月のそんなところがわたしは好きだ。  こうして待ちわびてやってくる四月三日。お飾りの日はもう、お祭りのようにはしゃいだものだ。蔵の重たい扉がゴロゴロと音をたてて開くと同時に、わが家にも爛漫の春が舞い下りてきた。緋色をした毛氈が畳の上に広がると、奥(座敷)は華やいで、いつもは冷たい顔をしている部屋も、このときに限ってやさしく子どもを迎えてくれたような気がする。夜には小さなおひなさんのお膳のうえに、ちらし寿司や小指ほどのだしまき、わけぎと赤貝のてっぽう和えなど、春の味覚が盛られていた。 こうして待ちわびてやってくる四月三日。お飾りの日はもう、お祭りのようにはしゃいだものだ。蔵の重たい扉がゴロゴロと音をたてて開くと同時に、わが家にも爛漫の春が舞い下りてきた。緋色をした毛氈が畳の上に広がると、奥(座敷)は華やいで、いつもは冷たい顔をしている部屋も、このときに限ってやさしく子どもを迎えてくれたような気がする。夜には小さなおひなさんのお膳のうえに、ちらし寿司や小指ほどのだしまき、わけぎと赤貝のてっぽう和えなど、春の味覚が盛られていた。この日を境に、糸がきれたように季節は堰を切って一気に走りだす。あれよあれよと口をあけているあいだにさくらは咲いて、惜しげもなく散っていく。いつも、これにとり残されては大変と急いでおひなさんを片付けたのだけれど、まったくその呆気なさといったら、まさにこれを春の夜の夢というのだろう。 大騒ぎをした大層なおひなさんも、今は昔。近頃は、すっかり静かなものになった。それでも、さくらのつぼみがピンクに染まりはじめると近所のお饅屋はんまでさくら餅とお団子を買いに自転車で走る。緋毛氈を一枚だけ床の間にしいて山桜のお軸をかけて、二月の終りに買っておいたひし餅とお菓子をお供えして、ごくシンプルな大人のお節句を楽しんでいる。花はさくら、なんといってもおひなさんには、この花がいちばんふさわしい。 (京町家再生研究会会員)
|
||
|