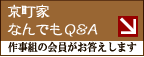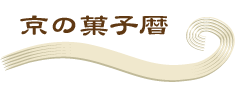 ※「京の菓子暦」は、平成14年(〜15年)の取材記事です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 明けましておめでとうございます。昨年の七月祇園祭の頃に始めた「京の菓子暦」ですが、あっという間に半年が経ち、新年を迎えることとなりました。毎月末には、翌月のお菓子の取材と撮影をするのですが、その前に題材を何にするか相談をいたします。そして、菓子職人さんには、実際より少し早い時期にお菓子を作ってもらうことになります。皆さまのご協力と温かいお言葉に励まされ、今年も京都の和菓子の魅力をお伝えしたいと思っています。 明けましておめでとうございます。昨年の七月祇園祭の頃に始めた「京の菓子暦」ですが、あっという間に半年が経ち、新年を迎えることとなりました。毎月末には、翌月のお菓子の取材と撮影をするのですが、その前に題材を何にするか相談をいたします。そして、菓子職人さんには、実際より少し早い時期にお菓子を作ってもらうことになります。皆さまのご協力と温かいお言葉に励まされ、今年も京都の和菓子の魅力をお伝えしたいと思っています。
和菓子は京都人の毎日の暮らしに密接に結びつき、生活と心を豊かにしてくれています。毎月のお菓子を紹介しながら、その奥にある京都の知恵と文化を探れたらと思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆お正月用の生菓子 一般のおうちでも、お正月にはお客様が来られたときにお出しできるようにと、生菓子を用意しておきます。生菓子といっても、お正月の三が日は日持ちがするようにしてあります。和菓子屋さんでは、年末のうちにお正月用の生菓子の見本を作って、それらを木箱に入れ、注文をとりに回ります。普通のお饅頭より一回り大きな「菊寿」や「巌(いわお)」は、おせちのお重箱用やお正月の進物用に使われます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お正月用のお菓子としては、昔からの縁起物、たとえば松竹梅や鶴亀をかたどったもの、その年の干支をなぞらえた形や焼印を使ったもの、勅題歌(今年は「街」)にちなんだものなどがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※「花びら餅」は、お正月のお菓子というよりも、裏千家の初釜に用いられることが多いお菓子です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
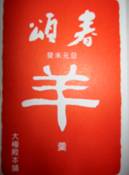 ◆羊羹(ようかん) ◆羊羹(ようかん) 和菓子の中で、「羊」の字がつくのが「羊羹(ようかん)です。 鎌倉時代に禅僧が点心の一つとして日本に伝えたといわれています。もともと中国で唐の時代に羊の肝などで作った回教の儀式用の料理があったことに始まり、日本では獣類ではなく精進のもので代用していった結果として、その名前だけが残ったと考えられます。「羹」は「あつもの」とも読み、お吸い物または汁物をさします。「羹」の意味が独立して、室町時代以後、現在の蒸し羊羹に似たものができたようです。一般に「丁稚羊羹」と呼ぶ、小豆に米の粉を入れて蒸したものです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 練り羊羹は、江戸時代の万治元年(1658年)に心太(ところてん)から偶然に寒天の製法が発見されてから出来たお菓子です。寒天というのは、寒晒心太(かんざらしところてん)から隠元禅師が名付けたという説もあります。寒天は、心太より臭みがなく透明度が高いので、お菓子には適しています。ちょうどその頃に南蛮貿易によって良質な砂糖が出回り普及していったので、それらを原料に用いる羊羹は高級化が進んだと思われます。羊羹に用いる寒天は、精製度が高い上質の糸寒天で、信州や丹波のものを使います。関西では特に丹波の寒天をよく使います。砂糖は、氷砂糖を砕いた「ざらめ」を用いるのが高級な羊羹となります。練り羊羹の古い看板の上部に「氷製」とあるのは、「氷砂糖(ざらめ)」を使っているということのようです。 練り羊羹は、江戸時代の万治元年(1658年)に心太(ところてん)から偶然に寒天の製法が発見されてから出来たお菓子です。寒天というのは、寒晒心太(かんざらしところてん)から隠元禅師が名付けたという説もあります。寒天は、心太より臭みがなく透明度が高いので、お菓子には適しています。ちょうどその頃に南蛮貿易によって良質な砂糖が出回り普及していったので、それらを原料に用いる羊羹は高級化が進んだと思われます。羊羹に用いる寒天は、精製度が高い上質の糸寒天で、信州や丹波のものを使います。関西では特に丹波の寒天をよく使います。砂糖は、氷砂糖を砕いた「ざらめ」を用いるのが高級な羊羹となります。練り羊羹の古い看板の上部に「氷製」とあるのは、「氷砂糖(ざらめ)」を使っているということのようです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 現在その種類は、練り羊羹、水羊羹、色や材質を変えて作る細工物の生菓子羊羹、砂糖を加えた寒天を固めた透明な錦玉液で作る錦玉羹(きんぎょくかん)や梔子(くちなし)カラメルなどで琥珀の色を付け良く煮詰めて日持ちの良い琥珀羹(こはくかん)などの夏羊羹、よく泡立てた卵白を加えた淡雪羹(あわゆきかん)、道明寺を入れた霙羹(みぞれかん)などがあります。 現在その種類は、練り羊羹、水羊羹、色や材質を変えて作る細工物の生菓子羊羹、砂糖を加えた寒天を固めた透明な錦玉液で作る錦玉羹(きんぎょくかん)や梔子(くちなし)カラメルなどで琥珀の色を付け良く煮詰めて日持ちの良い琥珀羹(こはくかん)などの夏羊羹、よく泡立てた卵白を加えた淡雪羹(あわゆきかん)、道明寺を入れた霙羹(みぞれかん)などがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
協力:大極殿本舗・六角店「栖園」 京都市中京区六角通高倉東入る南側 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の菓子暦へ
|