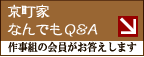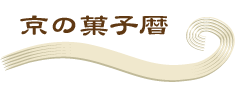 ※「京の菓子暦」は、平成14年(〜15年)の取材記事です。
|
||||||||||||
和菓子は京都人の毎日の暮らしに密接に結びつき、生活と心を豊かにしてくれています。毎月のお菓子を紹介しながら、その奥にある京都の知恵と文化を探れたらと思います。 |
||||||||||||
|
◆ひなまつり  「ひなまつり」は、「桃の節句」とも呼ばれます。桃は、中国では昔から、邪気をはらう縁起の良いものとされています。ちょうど季節の花として、桃の花が満開になる頃でもあるのですが、これは旧暦でのことなので、現在の三月三日では、まだ桃の花は咲いていません。また「百(もも)」にも重なり、長寿の意味も含まれているようです。ほかにも「よもぎの節句」「貝の節句」とも呼ばれるようですが、これは季節のものを付けて呼んだと思われます。 「ひなまつり」は、「桃の節句」とも呼ばれます。桃は、中国では昔から、邪気をはらう縁起の良いものとされています。ちょうど季節の花として、桃の花が満開になる頃でもあるのですが、これは旧暦でのことなので、現在の三月三日では、まだ桃の花は咲いていません。また「百(もも)」にも重なり、長寿の意味も含まれているようです。ほかにも「よもぎの節句」「貝の節句」とも呼ばれるようですが、これは季節のものを付けて呼んだと思われます。もともとは、陰暦の三月の初めての「巳(み)」の日を「上巳(じょうし)の日」として、「巳の日の祓い」を行ないました。人形(ひとがた)で身体をなでて、それを水に流して穢れを祓うというものです。この人形(ひとがた)が人形(にんぎょう)となって、ひな人形になったものと思われます。「上巳の日」には、水辺に出て厄を祓うのですが、その時に桃のお酒(後に白酒)を飲み、それらの行事が「曲水の宴」になっていったともいわれています。ちなみに平成十五年の「上巳の日」は、四月二日にあたり、旧の三月三日のひなまつりは、四月四日にあたります。ですから、四月三日にひなまつりをするというのもちょうど良いわけで、一番時候の良い、桜や桃のお花見に適した時ということです。  また、春のお彼岸の後の大潮のときに潮干狩りなどをして海辺で遊ぶ習慣が、先の「上巳の日」の節句と結びつき、その時季に一番美味しい貝を「海の幸」としてお供えしたようです。そして、菜摘み、摘み草というように、わらびやつくし、よもぎなどを摘みに野や山に出かけて、飲み食いなどして楽しむことも特に江戸時代には盛んになったようです。おひなさんのお飾りに「海の幸」「山の幸」があるのは、このような理由からではないでしょうか。 また、春のお彼岸の後の大潮のときに潮干狩りなどをして海辺で遊ぶ習慣が、先の「上巳の日」の節句と結びつき、その時季に一番美味しい貝を「海の幸」としてお供えしたようです。そして、菜摘み、摘み草というように、わらびやつくし、よもぎなどを摘みに野や山に出かけて、飲み食いなどして楽しむことも特に江戸時代には盛んになったようです。おひなさんのお飾りに「海の幸」「山の幸」があるのは、このような理由からではないでしょうか。そして、時代とともに「ひなまつり」は、おひなさんをひな壇に飾り白酒やお餅をお供えして、女・子供が遊び暮らす日となりました。
最初は、よもぎの入った緑色の「のし餅」と白い「のし餅」をひし形に切った二色でしたが、ハレの色の赤を重ねて三色とし、お祝いのお餅とするようになりました。五色五段のひし餅は、陰陽五行のおめでたい五色で表しています。一番下の茶色は土の色、緑色は植物を 表していると思えます。 ・草もち もとは、薬草で邪気を祓うということから、母子草(ははこぐさ)の汁を搾り、蜜と合わせてお団子にしたものが九世紀に日本に伝わったものといわれています。母と子をいっしょに「つく」のは良くないと、「もぐさ」など、その時季に芽の出た草で代用したようですが、それが「よもぎ」に代わって現在まで続いているようです。
「あこや」とも呼ばれます。あこや貝のことです。また、「いただき餅」とも呼ばれています。下部は、よもぎ餅を使うお店もありますが、緑色の「こなし」を使う場合もあります。上には、ピンクあるいは紅白の「きんとん」がのっています。 ※他にも「おひなさま」や「蝶」、「菜種(なたね)きんとん」などの生菓子は、一足早く春の到来を告げています。 |
||||||||||||
◆宝貝(たからがい) 大きな蛤(はまぐり)の貝殻を用いて作られています。中には「海苔巻」「玉子焼」「なると巻」などを模った、ひな菓子のいろいろが詰まっています。 ※蛤は、蝶番がはずせるのですが、合うのは一つだけ。ということで、昔からお嫁入りの道具に「貝合わせ」が持たされたといいます。その中には、小さい貝が360個入ってて、合う貝を見つけて遊びます。その後、かるた取りのルールに発展したといわれています。
|
||||||||||||
|
協力:大極殿本舗・六角店「栖園」 京都市中京区六角通高倉東入る南側 |
||||||||||||
過去の菓子暦へ
|